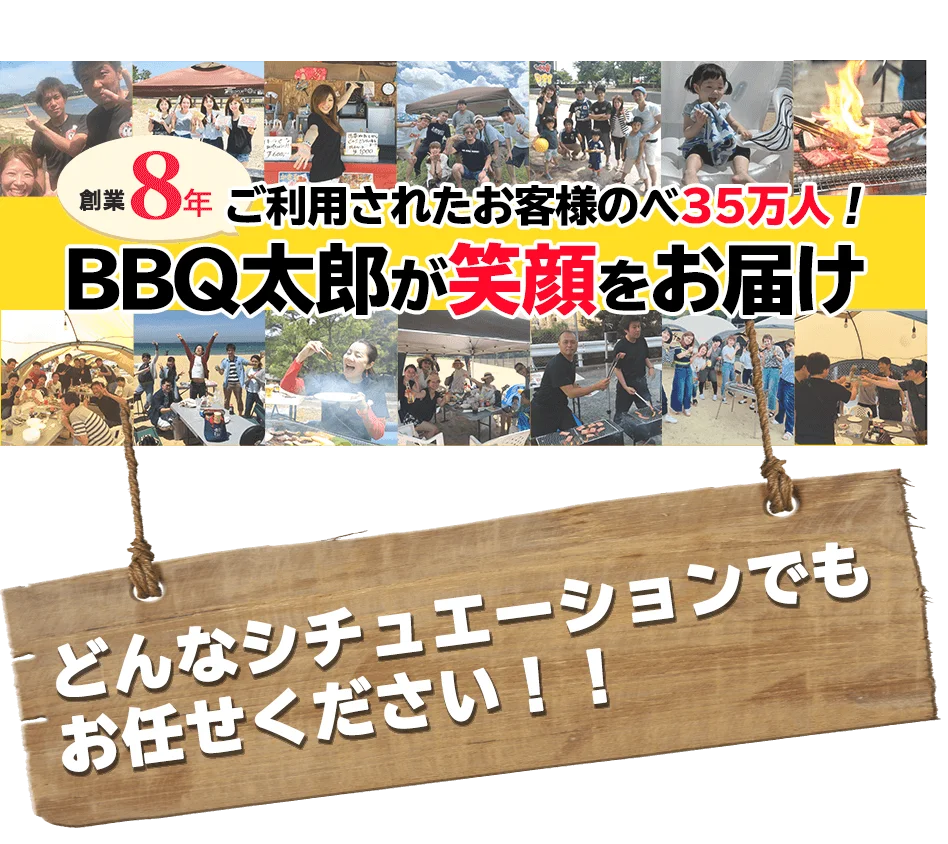茨城の郷土料理 たがねもち(🎌餅つきの由来と意味を知ろう!)
🥢 餅つきの由来と意味を知ろう!🎉
こんにちは!餅つきQ太郎 茨城店です✨
「たがね餅」の豆知識に続いて、今回は「餅つき」という行為そのものの🔍由来・歴史・意味合いについても掘り下げてみましょう。餅つきは、ただおいしいお餅をつくるだけではなく、古くから豊穣・家族・地域の絆を願う儀式的な行事だったのです。

🌾 餅つきはなぜ始まった?
日本において、米・稲はただの主食ではなく、〈神聖なもの〉として捉えられてきました。例えば「稲魂(いなだま)」「穀霊(こくれい)」といった表現があるように、稲作を通じて得られた「命」「豊かさ」「力」を象徴していたのです。
その米を「蒸してついて餅にする」というひと手間のある加工は、単なる食べ物を超え、「神様に捧げる」「力を頂く」「ハレの日にふさわしいもの」としての役割を持っていました。
また、餅つきは多くの人が集まって杵と臼を使ってつくもの。これによって「共同作業」「みんなで喜ぶ・分かち合う」という社会的・文化的な意味も併せ持っていたと言われます。
📅 年末年始に餅つきをする意味
お正月が近づくと、家族や近隣が集まって餅をつく風景が全国にあります。なぜ年末年始?それにはいくつかの意味があります。
- お餅は「鏡餅」などとして神様へのお供えに使われ、新年を迎える準備として12月中に仕上げておくのが伝統です。
- 12月28日や30日が餅つきに適した日とされ、29日は「二重苦」「苦持ち」と言われ縁起を担いで避ける地域もあります。
- 餅つき後にみんなで餅を食べることで、一年の無病息災・家族の繁栄を願う意味が込められています。
👥 餅つきが育む“絆”
杵を振るう人、返す人、蒸し上げる人…ひとつの餅をつく工程には役割があり、それぞれが動き合うことで一体感が生まれます。
この「みんなでつくる」作業自体が、家族・地域・世代をつなぐ大切な時間だったのです。
さらに、臼と杵には「男性・女性」「陽・陰」の象徴的意味があるという説もあり、子孫繁栄・家の繁栄を願う儀式性を帯びていたとも言われています。

🔧 現代における餅つきの意味
近年では、家庭での餅つきが減少し、機械化・イベント化が進んでいますが、それでも「出張餅つき」「もちつき大会」「餅つき体験」などが人気なのは、ただ餅を食べる以上の“体験”“文化”“共有”がそこにあるからでしょう。
例えば、餅つきの演出がある行事では参加者の記憶に残り、地域のPR・家族の思い出・絆づくりになります。私たち餅つきQ太郎茨城店でも、まさにその「伝統×体験」を大切にしています。
🎯 餅つきの由来を感じて「たがね餅」も楽しもう
「たがね餅」も、餅つきという儀式の延長線にある郷土餅です。茨城県南部の穀倉地帯では、米文化・餅文化が暮らしの中に深く根付き、「餅をつく」「餅を食べる」ことが、地域の喜び・節目・共有の象徴でした。
ですから「たがね餅をつく」「みんなでたがね餅を食べる」ということは、単に美味しいだけでなく、地域の伝統・季節・米への感謝・みんなで楽しむという意義があります。
餅つきの由来を知った上で、「たがね餅」を味わうと、その味わいもひと味深く感じられるはずです。ぜひ、来年の正月や地域イベントで「餅つき+たがね餅」の体験を取り入れてみてください!

📞 出張餅つきの予約・お問い合わせ
👉 餅つきイベント予約フォーム(茨城店)
☎ 050-6875-0762(餅つきQ太郎 茨城店)

📚 関連記事|餅つき参考コラム
- 👉 【保存版】餅つきの由来・道具・意味とは?子どもにも話せる豆知識まとめ!
- 👉 【保存版】餅つきのやり方をプロが解説!準備・手順・コツと出張サービスの選び方まで
- 👉 餅つきのプロが解説!ノロウイルス食中毒を防ぐ衛生管理のポイント
- 👉 【園児向け】おもちってなんでつくの?餅つきの由来をやさしく紹介!
- 👉 🍚 餅つき完全ガイド|蒸篭(せいろ)の蒸し方でふっくらおいしい餅を作る方法🔥
- 👉 【東京】餅つきイベントを丸ごとサポート|準備不要の出張レンタルサービス
- 👉 【関東】餅と郷土料理の文化図鑑|茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川に伝わる「もち」の物語